はじめに
大腿四頭筋のトレーニング方法として、一般的に膝関節屈伸運動や、Setting、スクワット、SLRなど様々なトレーニング方法が行われています。ここでは、エビデンスに基づいた大腿四頭筋のトレーニング方法について解説します。
大腿四頭筋に対するトレーニングの戦略と実践
以前の投稿で、「エビデンスに基づいた変形性膝関節症の治療」について解説しています。膝OAに対する治療方法の一つとして、運動療法が推奨されてきました。その中でも、下肢のトレーニング、特に大腿四頭筋のトレーニングが重要であることが述べられていました。
そこで今回は、Salliらの2010年に報告された論文について、解説していきます。
変形性膝関節症患者における2つの運動プログラムが様々な機能的アウトカム指標に及ぼす効果 :無作為化比較試験
結論から申し上げますと、この研究では膝関節の屈伸運動により、膝関節の疼痛や膝関節機能、QOLが改善した、という論文になります。
・対象者:45-65歳の両側膝OA患者膝関節
・運動内容:座位にて膝関節屈伸トレーニング、求心性運動(膝を伸ばす運動)と遠心性運動(膝が伸びた状態から、ゆっくりおろしていく運動)を行う
・運動頻度:週3日×8週間
・運動強度:70%MVC(最大筋力の70%)
・運動回数:膝関節の屈伸運動
5種類の等速性運動(60, 90, 120, 150, 180◦/s)、5種類の運動をそれぞれ10回ずつ行った
・比較対象は、トレーニングしない群をControl群としました。(すべての群で鎮痛剤の処方あり)
その結果、、
疼痛スコア(VAS安静時痛):初期評価 3.6 → 8週間後 1.2 →20週間後 1.4
疼痛スコア(VAS運動時痛):初期評価 7.1 → 8週間後 2.8 →20週間後 3.1 と初期評価に比べ、
疼痛の軽減を認めています。
このことから、膝関節屈伸のような大腿四頭筋のトレーニングは疼痛の軽減に効果がある、ということが証明されています。
大腿四頭筋に対するトレーニングの実際
臨床応用する場合、重錘などを用いて、RM法に基づき、今回の研究のような70%MVCなどの適切な負荷量を算出しましょう。
RM法は非常に簡便に負荷量を調節でき、以前の投稿でもRM法に基づく負荷量の調整方法について解説していますので、ぜひ一度、参考にしてみてください。臨床現場で治療効果のあるトレーニングが期待できるはずです。
回数については、10回(遠心性5回、求心性5回)×5種類=50回を実施していました。角速度は臨床では測定が難しいと思いますので、
臨床では一旦、同速度で求心性・遠心性運動を交互に実施していくこと(膝を伸ばす運動5秒、おろす運動5秒など)がいいでしょう。速度の変化が筋力向上に及ぼす影響については、後日解説していきます。
また頻度に関して、週3回×8週間のため、膝OA患者さんは外来で来られるケースが多いと思いますが、その場合は週1~2回は外来リハビリにて、残りは在宅にてホームエクササイズを実施していただくのがよいかと思います。重錘に関しては、最近では100円均一でも販売していますので、個人でご購入していただくのが、よいかと思います。
ちなみに以前の研究では、求心性運動のみより、求心性-遠心性運動の方が筋力増強効果が高いことが報告されていますので、「せっかく伸ばした膝を下すのであれば、遠心性収縮でゆっくりおろすようにしましょう!」
(今回の研究では、Biodexという機械を用いて、”MVCの測定”や”70%MVCでのトレーニング”を行っています)
まとめ
今回、大腿四頭筋のトレーニング方法の中でも、特に「膝関節屈伸運動が膝関節の疼痛や機能、QOLの向上に及ぼす影響」を論文を用いて、解説しました。
今回の運動は、遠心性・求心性運動を交互に5回ずつ行い(膝を伸ばす求心性運動後→ゆっくりおろす遠心性運動)、それを70%MVCにて5セット実施することで、疼痛軽減の効果が期待できます。
週3回を8週間続けるには、外来リハビリを週1~2回、残りを在宅にてホームエクササイズ実施していただくことが現実的です。


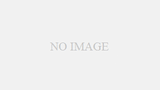
コメント