はじめに
今回は、理学療法プログラム立案のための考え方について解説していきたいと思います。
学生や経験年数の浅いセラピストの方々は、「授業では一通り習ったけど、いまいちピンと来なかった」、「統合と解釈が難しかった」、「プログラムを立ててみたけど、あっているか分からない」など理学療法プログラム立案に関する不安や疑問は多いと思います。
臨床にでてから数年かけて、プログラム立案までの考え方を理解していくことも多々あり、毎日の業務も忙しく、正しいやり方ができているのかわからないため、ストレスや不安が強い方も多いと思います。
そこで今回は、そういった悩みを解決でき、自分の中で考え方を咀嚼し、少しでも理解につながればと思い、理学療法プログラムの立案について解説していきます。作業療法士の方も立案までの流れは参考になりますので、是非一緒に確認していきましょう。
また、すでに理解されている方も、自分の考えが正しいのかどうか確認するために、参考にしていただければと思います。それでは、本題に入っていきましょう。
理学療法プログラム立案までの流れ、全体像について
まずはじめに、理学療法プログラム立案までの流れについて、全体像を考えていきましょう。
①理学療法評価
②統合と解釈
③問題点抽出
④目標設定
⑤治療プログラム立案
という流れになります。これについては、すでに授業で習っていると思いますので、
一つ一つ、丁寧に考えていきましょう
全体の流れ
まず、全体の流れから確認していきましょう。例えば、今回肩関節疾患を例に挙げて、考えてみましょう。
(Ex)五十肩(腕があがらなかったり、挙げたときに痛みのある疾患)の方が来院した場合
①「腕があがらなくなってきた」と言って来院した(関節可動域制限がありそうだ)
②腕があがらない原因はなんだろうか、と考える
→肩関節の筋肉が硬い(筋が短縮している)ために、腕があがらないのではないかと考える
➂治療プログラムとしては、肩関節のストレッチングをすることで改善していこう
最終的に、腕が上がるようになれば治療完了だ!
という流れになります。先輩セラピストの頭の中はイメージできましたか?
かなり簡略化しているので、ベテランの方はそこまでシンプルではないとコメントがありそうですが、今回はわかりやすくするために、簡略化した例で考えてみましょう。
具体例
少し具体的に、考えてみましょうか。
まず、
①「腕があがらなくなってきた」
→ 関節可動域評価を行う(肩関節のどの方向への動きが制限されているのかを評価する)
例えば、肩関節外転と屈曲に制限があったとします
②腕が上がらない原因はなんだろうか?
→肩関節周囲の筋肉が短縮しているため。ではどの筋肉が短縮しているから屈曲と外転ができないの?
例えば、ローテーターカフ(棘上・棘下・小円・肩甲下筋)などが短縮したことが原因で、腕があがらない(挙上や外転ができない)」ということにしましょう。
③肩関節のストレッチングをすることで改善する
→ストレッチングしたことによって、各筋肉の短縮が改善され、結果的に肩関節の可動域(挙上や外転)がよくなった。
つまり、①~③をまとめると、
①患者さんの抱えている課題を評価する(=可動域に制限があるな)、②その課題の原因は何だろう?、③原因を解決するために何をすればいいだろう?
ということになります。
よくある考え方
ここで、考えられるのは、①と③だけで考えてしまうことはありませんか?
①腕があがらないため来院した、③ストレッチングをすればよくなるはずだ
しかし、ここで説明したように②の過程が抜けていると、原因が筋の短縮ではなく、筋力低下だったとしたときに、ストレッチングばかりしていては、良くなるはずがありません。
そのため、②で述べた、「腕があがらないのは、何が原因なんだろう」と考えることが非常に大切となります。
原因を考える
今回わかりやすいように、筋肉の短縮が原因と仮説を立てましたが、
もしかすると、「肩関節の筋力低下」が原因だったり、「炎症による肩関節の痛み」が原因だったりするかもしれません。
それを証明するためには、患者さんに「疼痛の評価をしてみて、痛みがないか」を確認したり、「MMTで肩関節の筋力を測ってみて問題がないか」ということを確認する必要があります。
①患者さんが「腕があがらない」といってやってきた
②原因はなぜだろうか??
(a)筋肉が短縮しているため → 〇関節可動域制限を認める
(b)筋力が低下しているため → ×MMT5/5で筋力低下は認めない
(c)痛みのため → ×疼痛評価VAS 0/100で疼痛は認めない
➂どうすれば、「腕があがるようになるだろうか?」
上記の結果から、「腕があがらない」原因は、(a)筋肉が短縮しているためであると考える。
そのため、治療プログラムとしては、ストレッチングを実施する
という流れになります。いかがでしょうか? このように、「原因はなんだろう、と仮説を立てて、それを理学療法評価によって検証すること」、そしてその検証により「治療プログラムを決定する」ことが重要であると考えます。
ここで疼痛評価・MMTをすることで、疼痛や筋力に問題がない(例えば疼痛評価でVAS 0/100、肩関節のMMTは5/5)ならば、筋力や痛みは、今回問題の肩関節の挙上や外転の制限要因ではないことが確認できます。
このようにして、授業でならったような理学療法評価を行うことによって、原因を絞り込んでいきます。=この作業(仮説をたてて、理学療法評価の結果をもとに、1つ1つ検証していく作業)が、統合と解釈になります
まとめ
今回の例でいうと、肩関節の挙上や外転ができない原因は、何なのか?痛みなのか、筋力なのか、筋肉の短縮なのか?原因を特定するために、理学療法評価によって1つずつ評価を取り、検証していくことで、それぞれの要因が原因なのか、原因ではないのかを確認することができました。
今回の例のような「腕が上がらない」原因については、自分で勉強していくしかありません。腕が上がらない原因の引き出しをどれだけたくさん持てているか、が臨床家の腕の見せ所です。またその原因については、当然、自分で勝手に考えた仮説ではなく、医療書籍などを根拠にして、腕が上がらない原因は過去の書籍で「ここの筋力が弱くなると腕が上がらなくなる」「受傷直後は炎症で痛みが出やすいから腕が上がらない」など述べられている根拠を述べなければありません。では、その書籍はどこにあるの?どの本を読めばいいの?という方には、これがおすすめです。
「肩関節拘縮の評価と運動療法」赤羽根先生が書いている書籍ですね、これは治療効果が高いと思いますので、1~3年目で困っている方はぜひ参考にしてみてください。
またわたしの過去の稿でも、腕があがらない原因はなぜか?、膝関節の痛みの原因は?、高齢者の転倒の原因は?などの稿で他の疾患や症状についても説明していますので、参考にしてみてください!こうやって、引き出しを増やして、臨床力をどんどんつけていきましょう!患者さんを治せるセラピストが一番本物のセラピストです!皆さん、頑張っていきましょう!
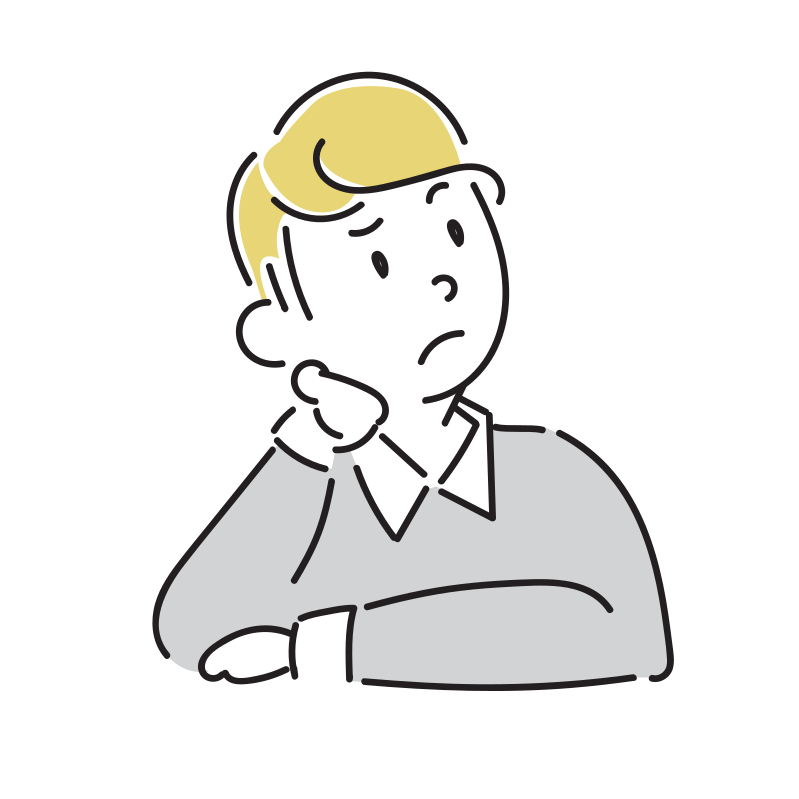
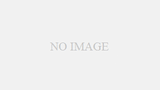
コメント