はじめに
今回は、メタボリックシンドローム(以下、MetS)のリスクファクターについて解説していきたいと思います。これまでは、理学療法士が介入できる可変要因として、身体活動量の低下に対して運動習慣の見直しや効果的な有酸素運動の指導などが推奨されてきました。
今回は、2013年に日本整形外科学会が提唱したロコモティブシンドローム(以下、LS)が、メタボリックシンドロームの発症に影響することを報告した論文がでましたので、解説していきたいと思います。
ロコモティブシンドロームはMetS発症のリスクファクター?
結論から申し上げますと、LSはMetS発症のリスクファクターです。さらに今回の研究では、双方向の影響について調査しており、MetSはLS発症のリスクファクターであるかどうかについても調査しておりますが、こちらについては有意差を認めなかったため、MetSがLS発症のリスクファクターとは言い切れないようです。それでは、詳細について、確認していきましょう。
目的
この研究は、
「LSとMetSの関係は双方向(お互いに影響し合う)のか?」
を調べるために、日本の製造業の労働者5010名を対象に6年間追跡したものです
対象と方法
対象者:40歳以上の労働者5010名
期間:2016年〜2022年
LSの評価:
- 2ステップテスト
- 立ち上がりテスト
- GLFS-25
MetSの評価:腹囲+高血圧、高血糖、脂質異常症のうち2項目以上(日本メタボリックシンドローム診断基準検討委員会の基準を使用)
・腹囲(男性で 85cm以上、女性で90cm以上)
・高血圧 : ①収縮期血圧≥130 mmHg、②拡張期血圧≥85 mmHg、➂降圧薬の使用のうちいずれかに該当
・高血糖 : ①空腹時血漿グルコース値≥110 mg/dL、②抗糖尿病薬の使用 のいずれかに該当
・脂質異常症 : ①トリグリセリド150mg/dL以上、 ② HDL 40 mg/dL未満、➂脂質異常症治療薬の使用のうちいずれかに該当
結果
①LSがある人がMetSを発症しやすいかどうか
LSがない人に比べて、LSがある人ではMetSを発症するリスクが1.34倍高い(HR 1.34)
特に2ステップテスト・立ち上がりテストが低い人でリスクが高かった
②MetSがある人 が LSを発症しやすいかどうか
MetSがLSの発症に与える影響は有意ではなかった(HR 1.07)
以上より、LS→MetS発症への影響はある、つまりLSはMetSのリスクファクターであると言えますが、MetS→LSへの影響については認められなかったため、逆方法の関連性は今回の結果からは言い切れないようです。
まとめ
今回の論文の結果から、
・ロコモティブシンドロームはメタボリックシンドロームのリスク因子であること
・逆方向(メタボ→ロコモ)は明確な関連が見られなかったこと
・職場での運動器の機能維持が、生活習慣病予防において重要であること、
がわかりました!
このことから、ロコモの予防はメタボの予防につながるため、ロコモティブシンドロームの予防的介入を開発することが今後重要な課題となっていきます。
また職場の健康づくりにおいても、ストレッチ・筋トレ・歩行トレーニングなどを推進することが有効であることも示唆されます。
最近では、企業において定期健診時にロコモ評価など運動機能評価を含めた体力測定を導入している企業も多く、今後は積極的に運動機能評価を取り入れ、理学療法士による介入が重要となってきます
参考文献
1)Yoshimoto, T., Shinozaki, T., & Matsudaira, K. (2025). Bidirectional association between locomotive syndrome and metabolic syndrome: A 6-year longitudinal study in Japanese workers. Preventive Medicine, 198. https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2025.108334

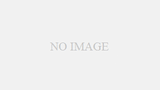
コメント