はじめに
今回は、メタボリックシンドローム(以下、MetS)の発症や進行に身体活動量が影響するかどうかについて解説していきたいと思います。理学療法士の方であれば、在学中の授業などで代謝性疾患(いわゆるMetSや肥満、糖尿病患者)に対して、運動療法として有酸素運動や、身体活動量の増加が推奨されている、と習っている方が多いと思います。
そこで今回は、その基礎となる論文についてご紹介していきたいと思います。
メタボリックシンドロームの発症に身体活動量が影響する?
メタボリックシンドロームの発症について
結論から申し上げると、MetSの発症に身体活動量は影響しています1)。その中でも、特に身体活動の量によってMetS発症への影響が異なり、さらに言うと身体活動量が多いほど、発症リスクが減少するという結果でした。
それでは早速、MetS発症と身体活動量の関係について解説していきます。
対象者
622名のMetSを持たない中年男性
評価
過去12か月の身体活動量をIPAQにより評価
IPAQ(国際標準化身体活動質問票) はWHOワーキンググループによって作成され、日常生活での身体活動量(Physical Activity)を定量的に評価するための国際的な質問票です。
IPAQは、Short版とLong版があり、Long版は仕事・移動・家事・余暇などの場面ごとに詳細に質問、Short版は7問の質問項目で構成され、歩行・中等度・強度の身体活動量を簡便に把握することができます。
結果
週3時間の中強度または高強度のLTPA(生活習慣に関連する身体活動)を行った男性は、座りがちな男性(週60分未満の運動)に比べてメタボリックシンドロームを発症する確率が低かった (年齢、BMI、喫煙、飲酒、社会経済的地位、インスリン、血糖、脂質、血圧など調整済み)
まとめ
今回は中年男性における身体活動量がMetSの発症に影響するかどうかについて解説しました。ある程度強い強度で身体活動量を継続することがMetSの予防につながる可能性があります。
今後は、介入研究についてもまとめていこうと思いますので、お楽しみに。
参考文献
1)Laaksonen, D. E., Lakka, H.-M., Salonen, J. T., Niskanen, L. K., Rauramaa, R., & Lakka, T. A. (2002). Low Levels of Leisure-Time Physical Activity and Cardiorespiratory Fitness Predict Development of the Metabolic Syndrome. In DIABETES CARE (Vol. 25, Issue 9).

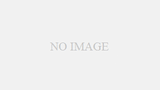
コメント